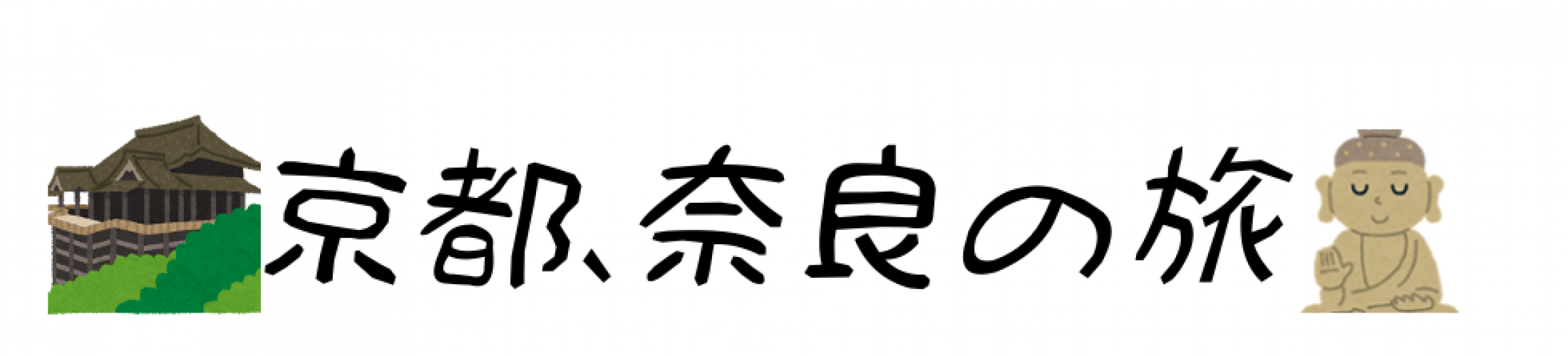「夜もすがら 月を三室戸 わけゆけば 宇治の川瀬に 立つは白波」のご詠歌(お寺を巡拝する人が、仏をたたえてうたう歌)で知られる
西国三十三所観音霊場10番目の札所で、本山修験宗の別格本山です。
京都随一といっても過言ではないアジサイの名所として知られ、「あじさい寺」とも呼ばれています。
三室戸寺の見どころとアクセス
ツツジ・しゃくなげ・アジサイ・ハスなど一年を通して多くの花々で境内が賑わい、またご本尊の霊験譚をはじめ、狛兎・狛蛇・狛牛にまつわる観音様の霊験譚など、数々の伝説に彩られたお寺です。
拝観時間・拝観料など
| 4月~10月 | 8:30~16:30(16:00受付終了) | 大人500円・小人300円 |
| 11月~3月 | 8:30~16:00(15:30受付終了) | (12月29日・30日・31日は休み) |
| つつじ・しゃくなげ園 4月下旬~5月上旬 |
8:30~16:30 | 通常の拝観料 |
| あじさい園 6月~7月初旬 |
8:30~16:30 | 大人800円・小人400円(昼夜入れ替え制) |
| あじさい園ライトアップ 6月中の土日 |
19:00~21:00(20:30受付終了) | 大人800円・小人400円(昼夜入れ替え制) |
| 蓮園 6月下旬~8月上旬 |
8:30~16:30 | 通常の拝観料 |
| ハス酒を楽しむ会 7月(開催日は毎年異なります) |
9:00~12:00 | 先着300名 500円 ※雨天の場合は中止 |
| 宝物殿 毎月17日公開 |
9:00より20分限り | 500円 |
| 「観音様の足の裏を拝する会」 11月~12月初旬の土・日・祝日 |
9:00より20分限り | 宝物殿にて 500円 (公開日は年によって多少違いますのでご確認ください) |
| 4月中旬~7月中旬の間、境内に「花の茶屋」がオープンします。 アジサイをイメージしたパフェやぜんざい、かき氷などがいただけます。 ※上記行事の開催期間は毎年異なりますので、詳細は三室戸寺公式サイトでご確認ください。 |
||
JR京都駅からのアクセス
1・JR京都駅からJR奈良線で「宇治駅」下車して徒歩35分
2・JR京都駅からJR奈良線で「黄檗駅」下車して、徒歩3分にある「京阪黄檗駅」から京阪宇治線・宇治行きに乗り換え「三室戸駅」下車して徒歩15分ほど
またはそのまま終点の「宇治駅」まで乗って下車して徒歩20分ほど
※JR・京阪どちらの宇治駅からも距離はありますので余裕があればタクシー利用が便利です。
徒歩で行かれる場合は三室戸駅が一番近いですが、駅にタクシー乗り場はないのでタクシー利用の場合は宇治駅で下車した方がよいでしょう。
ツツジやアジサイの頃にはJR・京阪どちらの宇治駅からも臨時の直通バスが運行されます。
運行期間は毎年異なりますので詳しくは京阪バスの公式サイトにてご確認ください。
三室戸寺と周辺の地図
ご本尊の霊験譚
宝亀元年(770年)光仁天皇が宮中に毎晩金色の霊光が差し込むのをご覧になって、その光の元を右小弁・藤原犬養に命じて尋ねさせます。
尋ね歩くと宇治川の支流・志津川の上流の清く澄んだ淵にたどり着き、その中から千手観音菩薩が現れました。飛び込んで抱き上げてみると一尺二寸(約36㎝)の二臂の像に変わっていたといいます。
このことを喜ばれた天皇が、御室(お住まい)をこの地に移し、奈良大安寺より行表禅師(最澄の師)を招いて、この像を御本尊としてお祀りしたのが当寺のはじまりで、当初は「御室戸寺」と称していました。
その後、御子の桓武天皇が最初に出現した千手観音菩薩を二丈一尺(約6m30㎝)の像として自ら彫られて、御本尊を体内に納めてお祀りされたと伝わります。
創建より光仁天皇・花山天皇・白河天皇と三人の天皇の離宮になったことから、御を三に変えて「三室戸寺」となりました。
寺伝では創建をこのように伝えていますが、伝説的な話が多くはっきりした事はよく分かっていません。
ご本尊は秘仏で二臂ながら千手観音菩薩とされ、2009年に84年ぶりに御開帳されて話題になりました。
飛鳥仏と言われるこの像は1479年の火災で堂塔が灰塵に帰し、桓武天皇の彫られた二丈一尺の仏さまも焼失してしまいましたが、その際に中より飛び出してきて難を逃れたと伝わり、火難消除の仏さまとしても信仰されています。
花の寺
京都には花の寺と呼ばれる寺院が多くありますが、こちらもそう呼ばれています。
春にはツツジ(約20000株)・シャクナゲ(約1000株)、初夏にはアジサイ(50種約10000株・開花期間中の土日にはライトアップもされます)、夏にはハス(古代ハス・大賀ハスなど100種250鉢)、秋には紅葉と一年を通して境内を花々が彩ります。
中でもアジサイは5000坪の庭園に10000株ものさまざまな花を咲かせ、京都随一の名所として多くの方が訪れます。(臨時バスが運行されるほどです)
桜・秋明菊・冬景色も美しく一年を通して様々な花や景色を楽しめます。
狛兎・狛蛇・狛牛
宇治の地は古来「菟道(うじ)」と呼ばれ兎と縁があります。
本堂裏の古墳は悲劇の皇子・菟道稚郎子(うじのわきいらつこ)のものと言われます。(兎と皇子の話は宇治神社の項をご覧ください)
狛兎の前にある大きな玉の中には、小さな卵形の石があってそれが立てば願いが叶うといわれます。
狛蛇はお寺に伝わる木像の宇賀神に似せて作られた大きな像です。
近くに残る民話に、三室戸の観音様を信仰していた娘の話があります。ある時、村人に殺されそうになっていたカニをその娘が助けます。
また違う日にその娘の父親が、畑で蛇に飲み込まれそうになっている蛙を見かけ、蛙を助ける代わりに蛇に娘を嫁にやることを約束してしまいます。
その夜、蛇は若者の姿になって娘を迎えにきますが、驚いた父親は三日後にもう一度来てくれと蛇を帰します。
約束の三日後に娘は固く戸を閉めて三室戸寺の観音さまを念じながらお経を唱え続けます。すると沢山のカニが現れてハサミで切りかかり蛇を退治してくれました。その後、お寺にお礼参りに行くと、参道近くの橋の上で悲しげに娘を見つめる蛇が現れふっと消えてしまいます。
娘はその蛇を供養するために、蛇の姿をした宇賀神を奉納したと伝わります。
宇賀神は財運・金運の神様で、この狛蛇を撫でると金運・良運がつくといわれます。類似の民話はあちこちに仏さまの霊験譚として伝わります。(今昔物語・蟹の恩返し等)有名なところでは山城の蟹満寺の縁起話がほぼ同じ感じでしょうか。最もあちらはもう少し蛇が凶暴だった気がします。
狛牛は勝運のつく宝勝牛
狛牛はおなかに小さなのぞき穴があって、そこから体内に納められた牛の木像が見えます。
この木像も観音様の霊験譚に由来するものです。
昔、百姓の夫婦がやっとの思いで子牛を手に入れますが、弱弱しいので毎月三室戸寺の観音詣での時に境内の草を食べさせていました。
するとある時、牛が何かを吐き出しまし、夫婦はその玉を「牛玉」として大切にしまっておきました。
その後大きく育ち立派な牛になり、観音様のおかげと夫婦は喜んでいました。この牛が評判となって是非自分の牛と闘わせてほしいというものが現れます。夫婦は断りますが、夢に牛が出てきてぜひ闘わせてほしいと懇願します。
そこで闘牛を行うと見事勝利し、沢山の賞金を手に入れそれを元手に牛の仲買をはじめ大金持ちになりました。
年老いて仏門に入り、大切にしていた「牛玉」を体内に納めた牛の木像を三室戸寺に奉納しそれがこの木像と伝わります。
口の中にある玉を撫でると勝運がつくといわれ「宝勝牛」とも呼ばれています。
阿弥陀三尊像の両脇侍は跪坐像
境内には親鸞聖人の父「日野有範」の墓だったと伝わる阿弥陀堂や国の重要文化財に指定されている十八神社本殿、宝物館には清涼寺式の釈迦如来立像・毘沙門天立像・阿弥陀三尊像を有し毎月17日に公開されています。(詳しくは上記の表を参照してください)
また11月~12月初旬の土・日・祝日に「観音様の足の裏を拝する会」が開かれます。
こちらのお寺の阿弥陀さまの両脇侍・観音菩薩と勢至菩薩は、有名な三千院の両脇侍の菩薩さまと同じで「跪坐(きざ)」像です。
大和座りとも呼ばれ正座をされているようなお姿で、三千院の像はすぐにでも動き出せるようにと少し前かがみになったお姿ですが、こちらの菩薩さまは本当に正座をされているような感じで、裾からちょこんと指先が見えています。
普段は正面からしか拝むことができないのですが、拝する会の時だけ後ろからこの指先を見せていただけます。
秋の紅葉の季節ですので合わせて楽しまれると良いかもしれません。なお、毎年公開開始・終了日が異なりますのでご確認の上お出かけください。