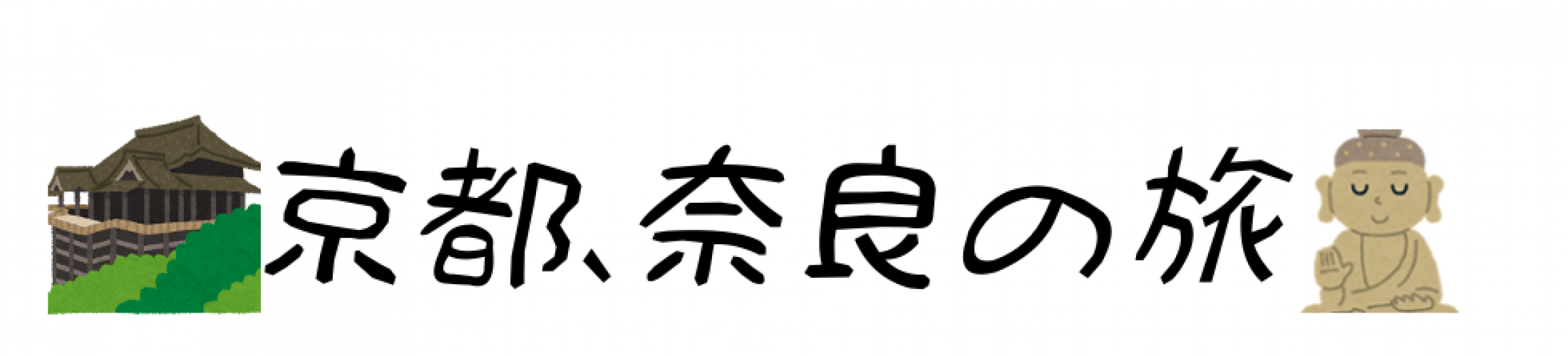2020年は大河ドラマで明智光秀が主人公となる「麒麟がくる」が放送されることで脚光を浴びる、この武将にゆかりの地が京都には多くあります。
こちらではそんなゆかりの地をご紹介してゆきます。
「三日天下」や「本能寺の変」など謀反人としてあまり良いイメージはない感じですが、丹波攻略の際の拠点になり、恩賞として領地となってから善政を敷いたといわれる亀岡や福知山では良き領主様としていまでも慕われています。
本能寺の変ののち秀吉との山崎の合戦に敗れ、敗走途中の小栗栖(京都府伏見区)で襲われ致命傷を負い自刃。明智藪が最後の地として伝わります。
首は居城だった坂本に持ち帰られたとも・亀岡の谷性寺に葬られたとも、娘の玉(ガラシャ)に送られ葬られた(宮津の盛林寺)ともいわれ、また土中に埋められたのち・胴体とともに掘り起こされ粟田口に晒されたのちに、数千人の首級とともに埋められ首塚が築かれていたものを、光秀の子孫が譲り受け祀っていたものが現在の白川にある首塚に移され祀られているともいわれ、それぞれに首塚が残ります。
必ずしもアクセスのよい場所ばかりではありませんが、ゆかりの地を巡って思いをはせれば何か感じるものがあるかもしれませんね。
京都駅から公共交通機関を使って各所へのアクセス方法はこちらのページでご紹介しています。
また各地域にある観光協会などの公式サイトもそちらで合わせてご紹介しています。今回ご紹介している地域は京都駅からかなり離れているうえに、電車やバスが一日に数本という場所もあります。京都市内のようにサクサクゆかりのスポットをまわることは難しいですので、地域の観光協会などで紹介されている周辺の観光地と合わせてのんびり楽しむことをおすすめします。
明智光秀と細川ガラシャゆかりの地と各所の簡易解説
宮津市・京丹後市
宮津市には玉(ガラシャ)ゆかりのスポットがあります。ガラシャの嫁いだ細川家が丹後攻略ののちに領地として与えられ、宮津城を築城し城下町を整備しました。本能寺の変ののちにガラシャが幽閉された地や光秀の首塚もあります。
宮津城から北へ3㎞ほどには天橋立もあり、京都市内とは違った海の京都が楽しめるスポットでもあります。
天橋立観光協会公式サイトでは周辺の観光案内などがされていますのでそちらもご覧ください。
宮津城跡
細川家が丹後攻略ののちに領地として与えられ築城し城下町を整備しましたが、今では城跡が残るのみです。
築城は細川忠興の父・藤孝が行っていますが、本能寺の変の際に光秀との非協力を示すために出家し幽斎となり田辺城に隠居したため、忠興の居城となりました。
関ヶ原の戦いでは幽斎は田辺城に籠城し、宮津城を焼き払ってしまったため細川家当時の遺構として残るものはありません。
のちに京極家など目まぐるしく領主が変わり拡張や改築も行われましたが、廃城になってからは市街化が進んでいましたが、2010年に城壁が復元され、太鼓門も移築されるなどして大手川沿いが整備され、生誕450年を記念して建てられたガラシャ像などもあります。
北へ3㎞ほどには天橋立があります。
盛林寺(せいりんじ)
丹後を制する前の領主に続いて、勝竜寺から移った細川氏にも庇護されたお寺です。本能寺の変ののちに光秀の首がガラシャに送られ葬られたとの伝承があり位牌も祀られていて、裏山には首塚(供養塔/宝篋印塔・ほうきょういんとう)があり、供養塔の基礎の両側には天正10年6月13日篠鉄光秀居士と刻まれています。
なおガラシャのいたころの盛林寺は現在地ではなく、二度移転しています。
味土野(みどの)
本能寺の変ののち、謀反人の娘となったガラシャが離縁され幽閉された地です。味土野(女城・めじょう)にガラシャが、近くの男城におつきの家来たちが住んだ(または監視役の武士たちが住んだとも)とされ邸宅跡が残ります。
数年後に秀吉のとりなしで復縁していることを考えれば、幽閉というよりは保護されたと考えられるのかもしれません。
今でも味土野へ至る道は細く、徒歩や車かタクシーを使うしかアクセスできない場所で、雪深い冬には辛い生活を強いらていたことでしょう。
宮津城から味土野へは、須津峠を越え陸伝いに向かったという説や、舟を使って日置の浜に渡って途中 金剛心院で休息し向かったという説があるようです。
福知山市
福知山も亀岡同様に、丹波攻略ののちに光秀の領地となってから善政を敷いたことで地元の方々には慕われ、ゆかりの地が多数残ります。
福知山城
福知山城も丹波攻略ののちに領地となってから築城、城下町を整備し善政を敷いたといわれています。
城は明治に廃城とされ解体されましたが、石垣は野面(のずら)積みと言われ当時の面影を残しているといわれます。
現在では市民の運動によって天守閣が復元され郷土資料館として光秀ゆかりの品々が公開され、続日本100名城や日本の歴史公園100選にも選ばれています。
9:00~17:00(16:30受付終了)
大人320円/小中学生100円
火曜休館(休日の場合は翌日)/12/28~12/31と1/4~1/6も休み
蛇ヶ端(じゃがはな)御藪/明智藪(光秀堤)
由良川と土師川の合流地点はたびたび氾濫をおこし、地域の人々は水害に苦しめられていましたが、光秀が川の流れを変えさらに堤防と衝撃をやわげるために竹藪を築いたと伝わり、明智藪と呼ばれています。
伏見小栗栖にある光秀最後の地となったと伝わる明智藪とは別の場所です
御霊神社
もとはお稲荷様(宇賀御霊守・うかのみたまのかみ)を祀る神社でしたが、地元で慕われ冤罪で亡くなったとされている光秀が合祀され御霊神社になりました。光秀が制定したといわれる明智光秀家中軍法と書状2点が市の有形文化財に指定されています(現在は天守閣の郷土資料館にて展示)。
境内には諸願成就の「叶石」があり、知る人ぞ知るパワースポットとされ、また水害に苦しめられた記憶を残す堤防神社などもあります。
光秀ミュージアム(佐藤太清記念美術館2階)
福知山城公園内の佐藤太清記念美術館2階に2020年1月11日~2021年1月11日までの一年間限定でオープンするミュージアムです。
NHKの「麒麟がくる」の放送を機に光秀と福知山を知ってほしいとの企画展です。
2割お得な前売り券なども販売されていますので、興味のある方は福知山市公式サイトをご覧ください。
福知山にはウリ坊の背に乗るロデオ猿で人気になった「福知山市動物園/三段池公園内」や、北部は鬼伝説の残る大江山や元伊勢三社などがある自然豊かな地です。福知山観光協公式サイトでは光秀ゆかりの地をはじめとした市内の観光マップなどが公開されています。
亀岡市
亀岡は信長の家臣になったのち、丹波攻略を命じられた光秀が拠点とした地で、市内には戦の舞台になった城跡などが多数残ります。
攻略後の恩賞として賜ってからは街並みを整備し善政を敷いたといわれ、春に光秀を偲んで行われる「亀岡光秀まつり」では、甲冑姿の光秀をはじめとする武者行列や正室の熙子(ひろこ)、娘の細川ガラシャ(玉)や春日局姿の行列が市内を練り歩きます。
亀山城跡(亀宝城・きほうじょう/霞城・かすみじょう)
亀山城は丹波攻略中から築城が始まり、領地となったのちも普請が続けられたと伝わります。光秀亡き後は豊臣家によって、さらには徳川家によって修築され五重の層塔型天守閣が築かれるまでになりましたが、明治維新の後に廃城処分となり城跡は現在 宗教法人の所有となっています。
(宗教法人大本の所有ですので、そちらで受け付けをすると内堀跡や本丸付近の石垣を見学させていただけます。)
谷性寺(こくしょうじ・光秀寺/桔梗寺) 首塚
光秀がこちらの不動明王を厚く信仰し、本能寺の変の際には「一殺多生の剣を授け給え」と誓願して見事本懐を遂げたと伝わります。
本能寺の変ののち天王山で秀吉との戦いに敗れ、居城の坂本城まで敗走する途中の小栗栖で自刃。その際介錯をした溝尾庄兵衛(みぞおしょうべい)が近臣に光秀の首を不動明王の近くに葬るように託したと伝わり、「首塚」が建てられ命日の6月14日には回向が行われています。
門前には光秀の家紋キキョウの花が咲く「ききょうの里」があり、毎年6月~7月花の見ごろに約5万株の様々なキキョウが咲き乱れます。鉢植えのキキョウや地元の物産品の販売などもあり、ユリ・ヒマワリ・半夏生・ぎぼうしなど約1万5千株の花々が咲く花畑も楽しめます。
また11月下旬からクリスマスまではライトアップも行われていますので、詳細はききょうの里公式サイトをご覧ください。
西岸寺
丸岡城址(余部城)の本丸跡にあるお寺です。光秀による丹波平定の際に落城し砦として機能しました。周辺には「古城・ふるしろ」などの地名が残ります。
明智の戻り岩
亀岡から大阪方面へ向かう旧道にある法貴峠(ほうきとうげ)には屏風岩と名づけられた巨岩があります。
光秀が丹波平定に向かう途中、この巨岩に行く手をさえぎられ引き返したとも、羽柴秀吉の援軍に向かう際ここで引き返し本能寺へ向い信長を討ったとも伝わり「明智戻り岩」と呼ばれています。
※平成30年の台風被害によって近くまで近づけない状況になっています(2019年6月現在)。近くを通る国道423号から見下ろす形で見ることはできますが、歩道のない峠道ですので注意が必要です。
明智越え(亀岡から愛宕山へのハイキングコース)
「時は今 天が下しる 五月哉」本能寺進軍前に愛宕神社で催された連歌の会で光永が詠んだと伝わる句です。
光秀はたびたび愛宕神社を訪れていたと伝わり、亀岡城から愛宕神社まで参詣の際に通ったと伝わる道は「明智越え」と呼ばれ、現在はハイキングコースとして整備されています(平成30年の台風被害によって途中が危険な状況になっています)。
丹波国分寺跡
兵火によって消失、山門は亀山城の雷門に、毘沙門天は亀山城の守護として遷されたと伝わります(現在は聖隣寺に安置)
聖隣寺
秀吉の養子になった信長の4男が建立したと伝わる信長の供養塔があります。
こちらの毘沙門天像は、光秀が亀山城築城の際に守護神として二の丸に祀ったものとされ、のちに城主になった小早川秀明がこちらのお寺を建立する際の守護として遷したと伝わります。
西京区・長岡京市・乙訓郡・伏見区
この地域には本能寺の変ののちの史跡が残ります。
本能寺の変で信長を討ったのち秀吉と戦った天王山、娘玉(ガラシャ)が新婚生活を送り 天王山の戦いで敗れた光秀が逃げ込み最後の夜を過ごしたとされる勝竜寺城跡、城から敗走した際に通ったとされる道や自刃したとされる藪などがあります。
愛宕神社
標高924mの愛宕山の山頂にあり、将軍地蔵を祀ることから光秀も信仰していたといわれます。
たびたび参拝し亀岡城から愛宕神社まで参詣の際に通ったと伝わる道は明智越えと呼ばれ、現在はハイキングコースとして整備されています(平成30年の台風被害によって途中が危険な状況になっています)。
本能寺挙兵前には何度もくじを引き、その後に催された連歌の会では「時は今 天が下しる 五月哉」と詠んだとされています。
ふもとから歩いて片道約2時間(健脚な方が表参道を登った場合の時間です)の山道を登り降りするしかアクセスする方法はありません。
明智川(小鼻川・こばたけがわ)
本能寺の変で信長を討ったのち領地に戻る途中この地で落馬し、それを見て村人が光秀と気づかずおにぎりを差し出し、少し落ち着きなさいと親切な振る舞いをします。喜んだ光成は「東の火事がどこか当てられたら望みの物を与えよう」というと本能寺と即座に答えます。そして村人に対して望みの物を尋ねると、この地は水田にひく水が不足しているので川を通してほしいと申し出、直ちに着工したと伝わる用水路です。
実際には光秀は本能寺の変ののちすぐに討たれてしまい、その時にこの用水路を完成させたとは考えづらいようですが、丹波平定の際にこの地を補給基地として道や水路を整備した時のものではないかと言われているようです。
天王山/山崎の戦い
「天下分け目の天王山」この言葉は秀吉と光秀が戦ったこの地(山崎)での戦が、秀吉の天下取りへの契機になったとされることから、重大な局面を指す言葉として使われています。
実際は山の近くの湿地帯で戦が行われ、勝負が決したのは淀川沿いと言われます。
現在は山頂までハイキングコースが整備され気軽に登れる山になっていてます。途中には秀吉が軍の指揮を高めるために松に旗印を掲げたとされる場所や、古戦場の見渡せる展望台などがあります。大山崎町公式サイトではハイキングコースが写真付きで紹介されています。
本陣跡(御坊塚)/恵解山古墳・境野1号墳
山崎の戦いで光秀が本陣を置いたとされるのが御坊塚です。
これに比定される古墳が境野1号墳で本陣跡とされていましたが、近年では近くの恵解山古墳(いげのやまこふん)がその地ではないかとも言われています。恵解山古墳は国の史跡に指定されていてて、公園が整備されています。
戦国時代には様々な古墳で陣が敷かれ、古墳としては荒らされてしまった状況になってしまったところも多く、恵解山古墳も円墳部分は陣を置くために破壊され石室部分が失われていましたが、大量の鉄製武具などの副葬品が発見されたことから国の史跡に指定され、現在は古墳公園として整備されるに至りました。
境野1号墳は現在サントリーの敷地にあり立ち入ることはできませんが、敷地南の住宅側には案内板がたっています。
両古墳は歩いて10分ほどの距離で、どちらも付近からは火縄銃の玉や空堀跡なども見つかっています。
勝竜寺城跡
光秀の娘玉(ガラシャが)細川忠興に嫁いで幸せな新婚生活を送ったといわれ、山崎の戦いで敗戦した光秀が逃げ込み最後の一夜を過ごしたとされる城でもあります。
城からの敗走の際通ったとされる北門跡なども残り、近くの神足神社(こうたりじんじゃ)付近に残る土塁付近は敗走のルートではないかと言われています。
現在は城跡に公園が整備され日本の歴史公園100選にも選ばれています。また毎年11月第二日曜日には長岡京ガラシャ祭が行われ、輿入れ行列などが再現されています。
2019年11月には模擬櫓にある歴史展示コーナーが大河ドラマに向けてリニューアルオープンされます。
明智藪(伏見)と胴塚
明智藪は勝竜寺から坂本城へ至る途中にあります。居城である滋賀の坂本城へ落ちのびる途中、現在の伏見小栗栖で落ち武者狩りにあい討たれたとも自刃したとも伝わり、明智藪を境内地に持つ本経寺には供養塚があります。
また北東へ約1.6㎞ほどには胴体を埋めたと伝わる「明智光秀之塚/明智光秀胴塚」があり、個人の農園さんの直売所脇にひっそりと建っています。
胴体は首と繋がれ粟田口ではりつけにされ、晒されたともいわれています。
京都市内
京都市内には首塚や本能寺の変の舞台となった本能寺跡などが残ります。また妙心寺には光秀を弔うために作られた明智風呂があり、蘆山寺には念持仏と伝わる地蔵菩薩像(通常非公開・特別公開あり)が安置されています。
首塚(餅寅)
秀吉との戦いに敗れ首がこの地にさらされたとも伝わり、五重の石塔が祀られています。
塚への入り口にある餅寅さんは、光秀の子孫・明田理右衛門から江戸時代に託されたとするこの塚を、今も大切に守っていらっしゃいます。
住宅街にひっそりある本当に小さな祠で内部は公開されていませんが、小さな木像と骨壺・お位牌が祀られ、その様子がわかる写真が掲げられています。
本能寺跡と現在の本能寺
現在本能寺は三条寺町にあります。ここには信長の供養塔があり、遺骨の代わりに太刀が埋められていると伝わります。
信長の討たれた本能寺の変がおこった場所は南西約1.5㎞ほどにあり、寺跡には石碑が建つのみになっています。
蘆山寺
光秀の念持仏と伝わる地蔵菩薩像が安置されています。通常は非公開ですが特別展などで公開されることがあります。
信長の比叡山焼き討ちの際、このお寺も天台宗のお寺としてその対象となりましたが、正親町天皇が親書を光秀に下され焼き討ちされずに済んだことから、光秀ゆかりの念持仏がこのお寺に安置されているそうです。(この親書は正親町天皇女房奉書として国の重文に指定されています)
光秀の所持品は残っているものが少なく貴重な遺品になります。
またこちらのお寺は桔梗の寺ともいわれます。紫式部の邸宅跡で源氏物語を執筆したのもこの地と言われ、キキョウは昭和に作られた源氏の庭に植えられています。桔梗門を家紋とする光秀ゆかりの品を所蔵するお寺でキキョウの花とは、不思議な縁を感じますね。
明智風呂/妙心寺
妙心寺の塔頭・大嶺院の僧 密宗は光秀の叔父にあたり、菩提を弔うために浴室を建てたと伝わります。明智風呂(国の重文)と言われ現在は非公開、特別展の時には公開されることもあります。なぜ風呂なのか?というと、逆賊の汚名を洗い流すという意味合いがあったとお寺では伝わり、命日には施浴が行われたといわれます。
施浴とはお寺などの浴室を仏の功徳として一般に開放することで、家庭にお風呂などない当時では貴重なことでした。のちには個人が追善や供養のために行うようになり、施しを受けた人々はこの時に故人に手を合わせ冥福を祈ったといわれます。
法堂には光秀の位牌も祀られています。
天寧寺
山門からの眺望に比叡山をおさめる額縁門で知られるお寺です。改修工事の際に屋根裏から光秀の位牌が発見されています。
曹洞宗の寺院で光秀との関係は分かっていませんが、この地にあった比叡山の末寺松陰坊にゆかりがあるのではとの説もあり、ご本尊の上にあたるところから発見されているため、ひそかに大切に祀られていたのではないかと言われています。
非公開寺院ですので公開はされていませんが額縁門からの景色は自由に楽しむことができます。